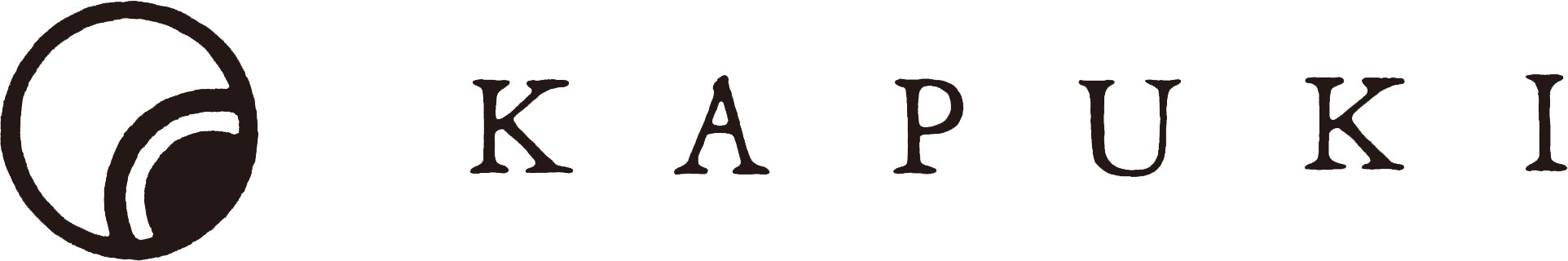「江戸のモードは世界で最も進んでいた!」丸山教授に聞く、江戸着物文化史。
(インタビュー 井嶋ナギ)
江戸のモードは、ヨーロッパよりも百年早かった。
── 先生のご著書『江戸モードの誕生』を読んで、江戸のモードはヨーロッパより百年早い、ということを知って本当に驚いたんです。
世界で初めて「モード」というものができた文化圏は、実は、日本なんです。もちろん、貴族などの特権階級の好みの変化っていうのは、日本も含めて昔からありましたけど、「不特定多数の人々を対象にした最新の流行」という意味でのモードは、江戸時代前期(17世紀半ば)に既に日本にできあがっていました。江戸時代のファッションブックである小袖雛形本のうち、現存する最古のもの(『新撰御ひいながた』)が寛文6年(1666年)刊行ですから。そのおよそ20年後の元禄期には、もうモードの完成期に入ってるんですよ。確実に、ヨーロッパより百年は早いですね。
── でもそんなこと、日本人は知らないですよね。モードというと、ヨーロッパが発祥だと思ってしまいます。
そうなんですよ。日本の文化の早熟度というのが、まるで忘れ去られてしまっています。「最新」という価値を消費するということ、そしてそれが都市文化の基盤を成しているということ、そういう意味でのモードが、江戸時代前期に既に誕生していた。そしてそれは衣服だけではなくて、芸能もそうなんです。歌舞伎が芸能として完成期を迎えたのは、元禄頃ですから、17世紀終わり頃。一方、ヨーロッパの市民音楽、モーツァルトのオペラなどは、18世紀の終わり頃。やっぱり江戸のほうが百年も早い。もちろんある程度の経済力は必要ですけれども、町人のような不特定多数の人々が関わることができた文化圏が、17世紀に既に成立していた。これは極めて特異なことだったんです。
── そうした先進性みたいなものが忘れられてしまったのは、いつからなんでしょう。
明治からでしょうね。明治に入って、欧米列強と渡り合わなければならなくなった時、日本はそれまでの自国の文化を消そう、忘れようとしたんです。明治政府のお雇い外国人だったベルツ、ドイツ人医師ですけど、彼は日本文化に興味を持っていろいろと日本人に話を聞くんですが、教養のある人、身分の高い人ほど、江戸時代を語らず、それは忘れてくれ、と言う、と(笑)。江戸までの日本は野蛮な国だった、という刷り込みが、ある教養レベル以上の人たちにはあったんです。そのせいで、そこで文化が断ち切られてしまった。だから、私たちが今、近代と近世をつなげようとすると、すごく引っかかる。どうしても壁があるんですよね。
「文様」というのは、実は、スゴイ存在である。
── 先ほど出た、着物のファッションブックである小袖雛形本は、文様の流行がメインなんですよね?
文様の紹介が目的ですね。江戸時代の着物は、小袖という形で統一されていますから。でも、文様っていうのは、実は、すごい存在だと思うんですよ。
── 文様はすごい、と。
そうです。普通、新しい形(文様)が現れたからといって、それをパッと表現して即座に根付くかと言ったら、根付きません。実は、何かをカッコイイとか美しいとか思うためには、背後に知識が必要になるんです。受け入れる側に相当の知識の基盤、壮大な知識体系がないと、無理なんですね。
話は古代にさかのぼりますが、当時の日本人が文様を作ろうと思ったとしても、価値があるとされるモチーフじゃないと浸透しない。当時、価値があるものと言ったら、輸入ものです。中国のものなら何でも憧れちゃっていましたから(笑)。たとえば、漢詩を読んで菊に憧れます。でも菊は大陸の植物ですから、菊を見たことがない。梅もそうです。とくかく舶載されたものに敬意を表する。そんな感じで、中国からさまざまな文様が輸入され、そうした文様を地紋として織り出した。それが現在、「有職文様」と言われるものとして残っているんです。普通、文様って何のモチーフかは分かりますよね? でも有職文様って、何のモチーフかよくわからないんですよ(笑)。それは当然なんです、日本にないものだから。西アジアを通って中国大陸を経由して入ってきた、外来の文様だからです。
── 確かに、有職文様の「浮線綾」とか、何なのかよくわかんないなぁと思ってました(笑)!
有職文様の「小葵」っていう柄も、実際の葵とは関係ないですしね。よく、「有職模様は日本の伝統的な文様です」とか解説されてたりしますけど、一番日本的じゃないものが有職文様です(笑)。だって、輸入されて、よくわからないながらも使い続けてただけの話ですから(笑)。日本的、と言われているものが、意外と日本的じゃなかったりするんですよ。
で、平安時代後期に「和様化」ということが起こってくるんですが、図様は有職文様だとしても、彼らは色を工夫し始めるんですね。襲の色目と呼ばれますが、色の組み合わせに、季節の植物の名前を当てはめていくんです。梅がさね、桜がさね、卯の花がさね、とか。それは、極めて日本的なんですね。日本って、とてつもなく四季が豊かなんですよ、世界的に見ても。四季の植物がすごくバラエティに富んでいるなかで、身近な植物を色の組み合わせの名称にしたのは、極めて、日本的です。
「文様」の知識体系は、家紋のなかに蓄積されていた!
── でも、襲の色目って、ものすごく複雑ですよね。
その通りで、色は抽象的ですから、継承していくのが難しかった。そもそも天然染料ですから退色しますし、光の加減でも変わりますし、伝言ゲームじゃないけど、次世代にこれが梅がさねですよ、と言っても正確に伝わらない。で、次の武家社会に継承されたか、っていうと、継承されないんです、複雑すぎて(笑)。武士たちは、もっとわかりやすいものを求めた。それが、文様なんですね。
たとえば、平安時代後期頃に、牛車などに装飾としての丸紋をつけるといったことが起こってきます。これが後に家紋の原型になるんですが、ここでやっと、身近なものをモチーフにし始める。有職文様だけじゃなくて、自分たちの文様を作るということをし始めるんです。
で、武家社会になると、武家は家というものをとても大事にするというのもあって、家紋が誕生します。で、あらゆるモチーフが集められ、あらゆる工夫がされていく。色から形へという変化と、家紋の中にいろいろ詰め込む、ということが平行して起こるんですね。室町時代になると、武家の装束で「大紋」という、家紋と装飾性を兼ねたものも普及します。ただ、文様を全面に表現するのは江戸時代以降で、それまでは衣服において文様を装飾の主役として前面に押し出す表現というのは稀だった。けれど、唯一、家紋だけは自由な工夫が積極的にされていたんですね。
実は、江戸時代になって、一気に文様表現が爆発することができた理由は、家紋のなかに文様の巨大な知識体系が蓄積されていたから、なんです。
── でも、なぜ、江戸時代に入って突然、着物に文様が表現されることになったんでしょうか?
現代まで続いている着物は「小袖」という形式の衣服ですが、これはもともと庶民の実用着であり、また公家たちが装束の一番下に用いる下着の形式でした。それが桃山時代の頃から、小袖が時代の中心的衣服になるんです。男女ともに、です。それまでは衣服の形式の違いによって男女の差を表していたのですが、男女ともに同じ形式の衣服になってしまったので、「性差の表示」が曖昧になってしまった。なにしろ、男か女かを示すというのは、衣服が持つもっとも重要な社会的役割のひとつですから、衣服形式にかわる何らか手法で性差を表示する必要が出てくるんです。そこで突然、文様が動き出してくるんです。女性の小袖に文様が集中し始めるんですね。
衣服っていうのはものすごく保守的なものですから、こうした大きな変化が短期間に起こるっていうのは、極めて異常なことなんです。ずっと変わらなかったものが、17世紀にイキナリ変わる。その要因は、小袖が男女共通の衣服になったために、文様で性差を表示しようとすることに求められたから、と私は考えています。
大きな変化を体現した、かぶき者や遊女たち。
── 江戸時代に入って、文様が急速にクローズアップされていくわけですね。
そうですね。ただ、そうした大きな変化が起こる際には、まず最初にカラを破る人間の存在が必要です。それが、かぶき者や遊女たちだったんです。その当時の、江戸時代初期までさかのぼる遺品はありませんが、当時流行した風俗画は残っています。そうした絵画に登場するかぶき者や遊女たちの小袖には、非常に大胆で大柄な文様が描かれている。そこに出てくる文様は、後に小袖雛形本で紹介されることになる文様も見えますし、後に歌舞伎役者の市川團十郎が流行させたことで有名な「かまわぬ」の柄も、もうこの時代に登場してます。とにかく、「目立ちたい」が第一だったんです。
── 「目立ちたい」が第一とは、親近感がわきます(笑)。でも、そうしたかぶき者や遊女たちは、どこからそうした柄を考案してきたんですか?
たとえば当時の高級遊女たちは、身分の高い人々と付き合っていたので、そこから影響を受けるし、識字率も高かったですし、教養のある人たちと対等に渡り合うためにやっぱりいろいろ武器を仕込んでいたでしょうね。かぶき者と言われる人たちにもいろいろな身分の者がいて、町奴という庶民の者もいれば、武士の旗本崩れのような者もいた。ですから、こういう小袖を作りたいということがあれば、それを注文するルートはいくらでもあったでしょう。かぶき者だとか遊女だとかいっても、単なるアウトローではなくて、教養という武器をもって、社会のシステムにしっかりとした居場所をもっていたんですね。
── 実際、かぶき者というのは、どのような存在だったのでしょうか?
かぶき者というのは、後の歌舞伎役者のことではなく、「かぶいている」者のこと。奇抜で常識はずれな行動や格好をする者たちのことです。戦乱の世が終わって社会が安定すると、武芸に優れた人よりも、学芸に優れた人が重用されるようになっていきます。すると武芸第一で鍛練してきた人たちの活躍する場がなくなってしまうわけです。そうした社会的な不満分子が、かぶき者と呼ばれる存在になっていったという経緯があります。
ただ、かぶき者には若衆と成人の二種類あって、成人のほうは今お話したような社会的不満分子が主体ですが、若衆のほうは男色の対象にもなってくる。遊女の男版のような。当時は、男色はそんなに珍しいものではないですから。江戸中期までは、大名クラスの武士が若衆に入れあげてパトロンになる、ということもしばしばでした。
ちなみに、今で言う芸能としての歌舞伎は、お国という女性が「かぶき踊り」を始めたのがルーツと言われていますが、そうした遊女による芸と、若衆による芸と、併存して行われていたんです。で、遊女歌舞伎は風紀を乱すということで禁止になり、さらに若衆による歌舞伎も禁止されて、野郎(つまり成人した男性)による歌舞伎だけが許されて、それが現代の歌舞伎につながっています。そういう意味で、若衆と遊女は、色も売り、芸も売り、という形では共通した特徴がありました。
江戸時代前期に出現した、世界初のファッションブック。
── そうしたかぶき者や遊女たちによる自由な文様を経て、小袖雛形本という世界初のファッションブックが出現するのですね。
寛文6年(1666年)に刊行された『新撰御ひいなかた』の序文に、この本には新しいものを取り入れています、今までの古いものは取り入れてません、と明記されているんです。つまり、新しい、ということを重要視している。しかも、版本ということは不特定多数の人に向けて発信しているということになる。そういう意味で、世界初のファッションブックと言って間違いありません。そして「最新」に価値を置くようになるということは、それは「流行」の始まりということを意味しています。面白いということだけでは、流行にはなりません。新しい、ということに価値をおいていることに意味がある。新しいということは必ず古くなるわけですから、古くなったらまた新しいものを供給するわけです。現に、元禄5年(1692年)の『女重宝記』に、この頃の流行は5〜8年でみな廃れる、と書かれています。
── 江戸時代前期に、もう流行のサイクルというものが意識されていたわけですね!
でも、そうした文様で小袖を美しく装飾する時代は、実はそんなに長く続かないんです。寛文年間(1661〜73)を中心に隆盛した寛文小袖がピークでしょうか。いろいろな理由があるんですけど、一つは、元禄期頃から帯の幅が広くなってくるんですね。そうすると、文様が腰で分断されてしまいますから、腰から上の文様と下の文様と分かれていく。それと、友禅のような細密な文様表現の技法が普及してくるので、細かな図様が流行し始めるということもある。もちろん、単純に大きな柄に飽きてきた、っていうのもありますね。飽きる、ということは新しさが消費されていく、ということですから。
さらに言えば、新しいものを新しいものをと追っていくと、アイディアがどんどん枯渇していく。そのような状況が表面化してくるのが、享保期後半の1730年代くらいですね。その頃の雛形本を見ると、裾模様とか、さらには裏模様とかが出てくるようになるんですが。文様も、今までないものを求めているうちに、変なサルの文様とか奇抜なものが登場してくる(笑)。凝りすぎたものもある。たとえば、カキツバタって文様の定番なんですがそれはもう目垢がついちゃってる。で、漢字で書くと燕子花、ツバメの子の花、って書くんですけど、図案もそれこそ花の形をツバメにしちゃったりとかするんです(笑)。
そういう時代になると、京都に集中していた雛形本専門の版元も徐々に無くなってきて、18世紀の終わりには雛形本は終焉を迎えます。
それ以降、流行の中心は江戸になります。小紋とか、縞とか、無地とか、雛形本を必要としないデザインですね。見本帳があればいい。で、「いき」の文化になっていく。そうなってくると、小袖を着装したときの全体の姿が重要になってくるんですね。髪形とか帯との調和とか。そうすると、浮世絵が雛形本としての役割を担うようになっていくんですよ。江戸の中期から、浮世絵の中心は江戸ですから。絵画の中心と流行の中心が一体化していくんです。
── そうすると、スタイリングが大事になってくるということでしょうか。
非常に重要になってきますね。ちょっと不思議なんですが、幕府は着物に対する禁令は頻繁に出してたんですけど、帯に対してはあまり出てないんですよね。なので、浮世絵を見ても帯が立派なんです。これはどうしてなのか今後の課題なんですが。
江戸時代のような遊び心が現代の着物にも欲しい。
── 江戸時代の着物についていろいろお伺いしてきましたが、現代の着物についてはどのようにお考えですか?
江戸時代の人々は、文様に関してあらゆる可能性を試していたと思うんです。そういう意味で、今の着物があんまり面白くないっていうのは、そういう冒険心の欠如にあるのではないかと思います。日本の伝統工芸という枠におさめなきゃいけないという意識が、作り手の側で過剰に意識されているんではないでしょうか。冒険心というと大げさに聞こえるかもしれませんが、要するに江戸の人たちは文様で遊んでたんですよ、モードは遊びだったわけですから。いかに遊び心を演出できるかが、文様のもつ大きな役割だったわけです。
品格を重視していた武家たちだって、しっかりと文様で遊んでいます。御所解模様の小袖なんかには、たとえば、風景模様の中に滝、柴の束と瓢箪を配して謡曲の『養老』を暗示するとか、そういう謎解きの遊びの要素があった。現代の着物には、そういった遊び心がないですよね。あったとしても、変に遊ぼうとしてるというか…遊び方を間違えたものだったり。何ていうか、一見いい柄だなと思ってよーく見ると、ピエロがいたりするんですよ(笑)。
── ありますね、猫とか音符とか(笑)。この文様さえ無ければ…と思ったことあります。
あと、たとえば百貨店の方とお話したりすると、いいと感じるものがこちらと違うことがありますね。やっぱり、百貨店で売れるものがいい、とおっしゃる。それはもちろん悪くはないんだけど、面白みには欠けていたり。売れ筋だけ追っていくと結局は先細りになっていくと思うんですよね、無難なものになってしまいますから。もうちょっと、「良い」というものの基準をつくらなきゃいけない。その基準をどこに求めるかというと、江戸時代だと思うんです。小袖という意味での着物文化の原点は江戸にありますから。でも、江戸にさかのぼるものがなかなか出てこないんです。
── 面白いものが出てこないというのは、何が原因なんでしょうか?
今は、何でもできちゃうから逆につまらなくなってしまう、ということはあると思いますね。車のデザインもそうですよね。昔は丸ライトしか使えないから、丸ライトをいかにデザインの中に組み込んで面白くしようかと、周辺のデザインに凝ったりしてたんですけど、今はどんな複雑な造形でも簡単にできちゃうから、逆に面白くなかったりする。やっぱり何か制約があったほうが面白いんですよね。
そういう意味では、着物ってすごく制約があるわけですよ。衣服としての形態も決まってるし、着た時に綺麗に見えなきゃいけないわけですから、どこに文様を置いてどこが隠れるかっていうことを理解してなきゃいけないわけで。その制約を逆手にとって表現すればすごい面白いデザインができるはずなのに、何か、制約を活かしきれていない気がして。幕末とか明治なんて、普段隠れる場所に文様を置いて、それがちょっと動くと見える、というようなのもあったんですけどね。
やっぱり、着る側が良いものを見極められた時代は、作り手もいろいろできたわけですよね。こうやればわかってくれる、と。でも着る側に文様で遊ぶとか、そういう人がいなくなってくると、やはり、どうせわかってもらえないから、って安全策に行っちゃう。で、着る側もそういうものを見ると、ああ、着物ってこんなものか、って着なくなってしまう、ということがあると思いますね。
着物は「文様」を演出できる世界で唯一の衣服形式である。
── 先生はこれからの着物にどうなってほしいとお考えですか?
やっぱり江戸の意識に戻ってほしい。でもそこで問題になるのは、女性の着物の「おはしょり」ですね。江戸時代を考えるとおはしょりは要らないと思うんですけど、じゃあ現代の生活でおはしょり無しで、裾を引いて生活できるかというと、環境として難しいですよね。かといって、対丈で着物を着るというのは、帯の存在を否定することになってしまう。というのも、帯の幅が幅広になり、結び方も複雑になったのは、着物の裾の長大化と連動した結果ですから。対丈で着るなら、男性の着物と同じように細帯で充分でしょ、ということになってしまう。
── ただ、現在も、おはしょりをして対丈と同じような丈で着物を着ていますよね。ならばいっそ、おはしょりナシの対丈で着てもいいのでは、という意見もありますが…。
やっぱり、帯の下にあるおはしょりのボリュームって、実は重要だと思います。見た目として。まぁ、着付けの手間を考えると対丈のほうがラクに決まってますけど、そこは難しい問題ですよね。でも、浴衣なら対丈でもいいかもしれません。本当は、やっぱり裾を長く引いて、腰に複雑な帯結びがあって、ある程度のボリュームで髪を結って、初めていいバランスになるわけですが。でも、それは今では難しいことですよね。
── 最後に、先生の考える着物の魅力とは、何でしょうか?
やっぱり、文様でしょうか。着物は、文様を演出できるという、世界で唯一の衣服形式ですから。たとえ他の国でもそういうものがあったとしても、ごく一部の特権階級の晴れの衣服とか、芸能関係の衣装とか、制限付きのものなんです。だけど、日本の場合はそれが日常風景としてあった。そしてそれは、単なる衣服というだけではなくて、都市を彩る存在でもあったんです。日本の町の風景の色彩というのは、瓦の黒とか、漆喰の白とか、木の茶色とか、自然の緑とか、そのくらいだったでしょう。そんな中で、一般庶民が、赤とか黄色とか紫色とかのさまざまな「色彩」と「形」を目にする機会なんて、着物しかなかったはず。となると、着物は、単なる衣服にとどまらない、都市の景観のひとつだったと考えられるわけです。それはやっぱり、ヨーロッパとは違う、日本の着物の面白さだと思いますね。

- 丸山 伸彦
- まるやま のぶひこ
1957年、東京生まれ。武蔵大学人文学部教授。東京大学大学院人文科学研究科美術史学専修課程修士修了。国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授、金沢美術工芸大学美術科助教授を経て、現職。専門は服飾史、染織史。
「日本の美術340
武家の服飾」(1994年至文堂)、「江戸モード大図鑑ー小袖文様に見る系譜」(1999年国立民族博物館企画展示カタログ)、「江戸のきものと衣生活」(2007年小学館)、「江戸モードの誕生ー文様の流行とスター絵師」(2008年角川選書)など、著作、論文多数。