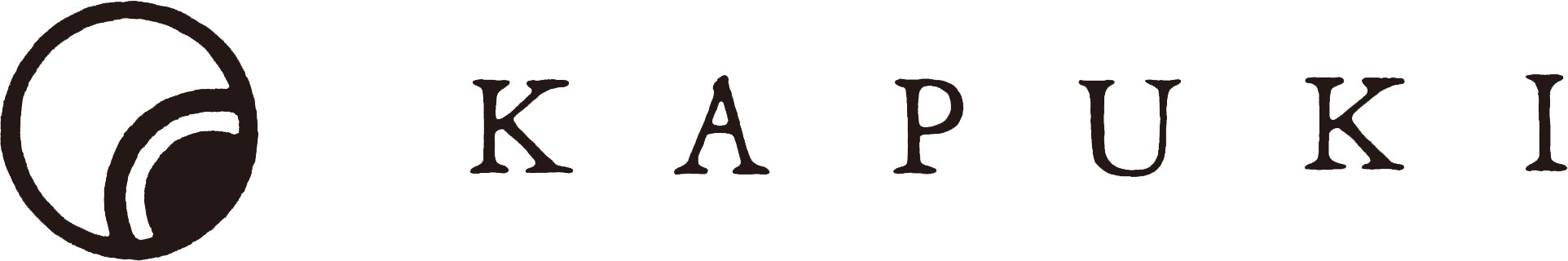Philosophy
KAPUKIの志
かぶく、という言葉がある。戦国時代の終わりに生まれた言葉で、
人を驚かすような奇抜な服装やふるまいのことを言う。
2014年、着物屋を始める時、この言葉に宿る精神を、貫きたいと思った。
何故ならば、着物は、かぶくことの連続だからだ。
「昔は女の衣裳もよう、其年ばへ相応の物を着し、今は左に非ず。丹後島人きれば、世間大方老若ともに着て、皆人まねをするなり。紋付、無地島類は、常の女と替るべきため、遊女巾広を用ひたり。今は常の女、皆遊女の真似をする」
「昔の女は年相応の柄を着たものだが、今はそんな奥ゆかしさは消えてしまった。丹後縞がいいとなれば、老いも若きも飛びついて真似をする。昔は遊女が紋付、無地、縞を着る時は、堅気ではございませんからと巾広の帯を締めてわざと派手にしたものだが、今は堅気の女が遊女を真似て巾広帯を締めている」(「八十翁疇昔話」より)
江戸時代の半ば、八十を過ぎた老翁が、“昨今の着物の乱れ”を嘆いた言葉だ。
「着物=伝統」「伝統は変えてはならない」「着物とはこういうもの」――着物と聞くととたんに始まるしかめつらの言説は、だから、嘘ばかりだ。私たちが今見る着物は、老翁が軽佻浮薄を嘆いたその時点から、変転また変転を繰り返した言わばなれの果てだ。けれどそれは着物が常に、現在形だったことを意味している。
だから、KAPUKIは、着物の常識を破ることを恐れない。
帯ベルト、おはしょりのない着物、普通よりずっと深く抜く衿の仕立て、黒色の美。
2014、2015‥‥2019、2020、2021年、今、この日常から立ち上る美意識を、ためらわず形にする。江戸の昔にいっとう最初に“丹後縞”を着て人々に憧れられた、名前も知れないかぶき女の心意気を、受け継いでいく。

一方で、着物には、かぶいてもかぶいても、残り続けて来たものがある。
花鳥風月、弓矢に垣根、舟、食物、時に貨幣まで。目に入るものを片っ端から採り上げて洗練のきわみにアイコン化した、数々の定番模様。つややかであたたかい、真綿紬の肌触り。帯に裾に残す大胆な余白の美。くすんだ色調を愛でること‥‥
それらを堅苦しい言葉で伝統と呼ぶのなら、KAPUKIは、伝統を深く礼賛する。そしてその生命が私たち日本人の精神のDNAに刻まれていると、強く、確信する。
かぶくこと。不動のもの。
着物の輝きは、常に二つの力の葛藤から生み出されて来た。長い長いその歴史に連なるものとして、KAPUKIは、これからも逆巻く葛藤を引き受けていく。
振袖のこと
振袖について話をしたい。
2018年、KAPUKIは、振袖ブランドを立ち上げた。それは、現在の振袖に対するKAPUKIからの異議申し立てだ。
いわゆる“普通の振袖”とされている振袖がある。
ぎらぎらした原色の地にこれでもかと模様が詰め込まれ、だから三十手前にもなれば着るのに気後れがする。そんな振袖だ。安価なものならまだいいが、結構な値段がつけられている――成人として歩き出す門出の日の着物が、これほどいびつな姿をしていることに納得がいかなかった。
だから、KAPUKIの振袖は、時代錯誤の少女性を押しつけたりしない。若々しく、けれど意志を宿したデザインは、袖を留め、時に色を変えれば一生の間楽しむことが出来る。
時代は、社会は、動いている。昭和はもうふた昔前の遠い話だ。
令和の女の子たちは、世界とつながり、自分の力で人生を切り開いていく。
その道のりに寄り添う振袖を、KAPUKIは届けたい。
KAPUKIの衣更え
そして、2021年7月11日。7年目のKAPUKIは、大きく衣更えをする。
これまでと同様、中目黒の川沿い。旧店舗からわずか3軒隣りの2階建ての新店舗はギャラリーを兼ね、着物と振袖の間にアート作品が宝探しのように現れる。
振り返れば、KAPUKIは、東日本大震災を原点として産声を上げた。
あの震災で、当たり前だった日常にひびが入り、その亀裂から漏れ出したシステムの歪みに目を開かされた。そして同時にシステムがふるい落として来たものを――明治の文明開化までさかのぼって――見直し始めた。その一つが、着物だった。
これから、KAPUKIがブックしていくのは、私たち日本人の出自と現在とを考察し、その葛藤の中から作品を生み出すアーティストたちだ。それは、KAPUKIが、この7年間、着物というメディアを通し繰り返して来たことと同じ根を持っている。
そして、窓の下を目黒川が流れ、春には満開の桜が広がる新しいKAPUKIを、世代も、職業も異なる人々がふらり、ふらりと集まって来る場所にしたい。その中に着物がある。着物は、愛すべき日本の伝統は、今も熱く息をしている。