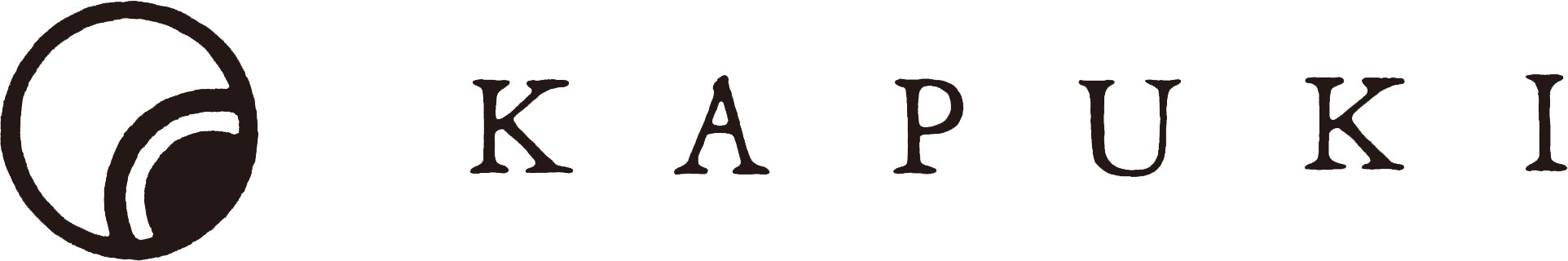山口源兵衛 インタビュー
─「“伝統”を錦の御旗にして、これが日本の伝統ですからって逃げ込む場所にしてる。」
山口源兵衛。親しみを込めて、“源兵衛さん”。その人との対話は、いつも刺激に満ちている。縄文の暮らしから、ヨージ・ヤマモトへ。アマゾンの未開民族から、シリコンバレーの起業家の信仰心へ。話題は孫悟空さながらに古今東西を駈けめぐるが、この日はひどく物騒な発言から始まった。
「第三次世界大戦の準備で忙しいんや」
源兵衛さんが座っているのは、京都の中心。気圧されるほど立派な構えの京町家の、更に奥座敷だ。江戸時代より280年続く帯匠「誉田屋源兵衛」。その十代目当主として、うるさがたの多い着物業界にあっても誰もが敬意を払う人物。けれど、5年前、まだよちよち歩きだったKAPUKIを分け隔てなく受け入れてくれた人でもある。一体今日は“第三次世界大戦”という言葉で、何を言おうとしているのだろうか?しかもそれはこちらから打って出て行く戦争で、敵はアメリカ、そしてヨーロッパだという。
「京都でも東京でも、今、この国を歩いたら、みんな洋服を着てるやろ」そう、話し始めた。「誰ももうおかしいとも思わんようになってるけど、これは “日本人がヨーロッパの民族服を着てる”ということや。それも150年間、明治維新からずっと」
その言葉には悔しさと、静かないら立ちがにじみ出ている。それも当たり前の悔しさではない。内臓をかきむしられるような激しい悔しさだ。
「もしも染織のオリンピックが開かれるとするわな。そうしたら、日本は選手としては参加しないで。だって金メダルが当たり前やから。日本は、特別審査員。僕はこの国の染織は、それくらいすごいと思うてる」
事実、誉田屋の一室には、すさまじい帯が並んでいる。筆で描いたのかと見紛うほどに、緻密、かつ繊細に織り上げられた山水風景。一方でそのすぐ隣りに掛けられた帯では、究極にそぎ落とされた幾何学模様が迷いのない直線で表されている。思い描くイメージのすべてを糸で具現化する技術が、この国には確かに存在しているのだ。

「日本というのは、太平洋のどん詰まり。海と陸のシルクロードを通って入って来たものが出て行かんでみんなここで止まって熟成する、そういう土地なんや。オリジナルは何もないけど、外から来たものを二千年間、一生懸命磨いて来た。その上江戸時代は鎖国したから、産業革命の波に百年乗り遅れたんやね。それで西洋に追いつくのにずいぶん無理することにもなったけど、向こうがとっくに棄てた手仕事の技が残ったのはええことやったと思う。1867年のパリ万博で、世界の人が度肝抜かれてる。だって、焼き物でやで、葉っぱに蛙が乗っかってるところを作って、そのよだれまでぽたっと、したたるように表現してたんだから。まさに超絶技巧やね」
そして、遠い昔のパリ万博だけではない。2015年から3年間、世界屈指の工芸美術館「ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A/英国)」のキュレターが、誉田屋を詣でた。そして帯七点、着物三点がパーマネントコレクションに収蔵された。コロナ禍で中止になったが、昨年、V&A主催の世界的な染織シンポジウムの大トリで、源兵衛さんが講演することも決まっていたという。世界は日本にひざまずいたのだ。
「だけどな、織物だけやないで。今日着てる、この浴衣の模様、これは江戸のはじめの屏風から見つけて復元したんや。大きな格子の模様を、大胆に崩してるやろ。格子っていうのは秩序やから、僕の考えでは、これは、幕府への反抗を表してると思う。こんなもん着てるヤツが京都の街をうろうろしてたんや」
そしてまたはじめのいら苛立ちに戻っていく。織りも、デザインも、染めも、先達たちがこれほど素晴らしいものを作り上げて来たのに、日本人が一番それに気づいていない、と。
「でももう仕方ないんやね。150年間、日本人は日本を棄てて来たんやから。祇園に入って来た若い子に三味線を教えようとしても、もう真っすぐには教えられんって。ドレミに直して初めて、ああそうかって分かるそうや。日本はそういう国になってしまった。和の音を聞いても、昔の人と同じ通りには耳に入らへん。音楽も、着るものも、それから経済も、そうやって支配されてしまってる」
そしてもっと悪いことだって起こり得る、と付け加えた。

「2年前やったかな、ヨーロッパのハイファッションブランドのコレクションを見て呆れたわ。明らかに「これ、着物やん」っていうもんやったから。ぼうっとしてたら、連中はみんな盗んでいってしまうで。挙句の果てにこっちにライセンス料払えって言って来るかも知れん」
だから、戦わなければならならない。植民地にされないために。明治の先輩たちは文明開化=西洋化することでその危機を乗り切ったが、今度は日本を前面に出して戦うのだ。そう、第三次世界大戦の始まりだ。
「日本人がドレミになってしまったのは、実のところ、日本人自身の問題もあると思う。明治の話やけど、外国人を桂離宮に案内して、侘びの美を代表する場所だと紹介したそうや。でもその外人はさっぱり分からんから、もう少し侘びについて説明してくれないかって。そりゃそうやな。ところが日本人は、そんなもんは説明出来ませんわと答えたらしい。えらい不親切やけど、でも、それも正しいのかも分からん。日本の侘び、寂び、そんな簡単に言葉で説明して分かるようなものではないわな。ここで暮らして、お茶でも、お能でも自分で何年もやって、それでだんだん分かって来るもんや。だけどな、そう言ってるうちに植民地になって何もかも消えてしまうんやったら、もう少し説明もしなきゃいかんのやないやろか」
源兵衛さんは相撲の土俵をたとえに挙げた。
「世界で戦う時は、世界のルールに乗らなあかん。世界の格闘技はリングでやるって決まってるんやから、そこに土俵を持って行ったって見向きもされないんや。だけど日本人は、特にこの着物の業界は、いつまで経っても、土俵や。“伝統”を錦の御旗にして、これが日本の伝統ですからって逃げ込む場所にしてる。せっかく世界一の技術があるのに、国内だけ、土俵の勝負のことしか考えてない。だけどそれでどうや、今になって、あの技術もなくなりそうだ、こっちもだ、誰も着物を着いひんって、慌ててる」
誉田屋は昨年、新ライン「NOBLE SAVAGE」を立ち上げた。その主軸である「HAORI」は、羽織やはっぴ由来のフォルムを取りながら、袖幅はぐっと細く、けれど洋服よりはゆったりとした仕立てで、ロングカーディガンのように着ることが出来る。
素材に用いたのは、アジア産の最上のシルクだ。そのシルクを日本の技法で染め、一部には、源兵衛さんが数十年にわたって収集した世界各国の希少な布を惜しげもなく使用している。羽織のようでいて、羽織ではない、HAORI。着物のようでいて着物ではない、世界へ乗り出していく新しいKIMONOの姿が、そこには立ち現れている――宣戦布告だ。
「KAPUKIさんもそうやし、ファッションでも音楽でもアニメでも、アメリカやヨーロッパの猿真似ではない、面白いものを作る人が日本のあちこちにぽつぽつ出て来ていて、すごくええなと思う。だけど、どれも単発で、全体としてのダイナミズムがないんや。そこがこれからの課題やね」
今は仕掛けていく絶好の時なのだと言う。
「ヨーロッパもアメリカもアイディアに行き詰って、だんだん極東に目が向き始めてる。さっき言った、まるで着物みたいなコレクションが出て来るのがその証拠や。だけど、本家はこっちやで。はじめはドレミでも構わへん。先輩たちが二千年かけて作って来たものに、ドレミでどんどんアクセスしたらいい。その時に大事なのは直感を大事にすることや。伝統とはこういうものですだの何だのうるさいこと言う人に惑わされて、ごちゃごちゃ勉強し過ぎん方がいい。直感で選んでいけば、必ず面白いもんが生まれて来る。だってこれはうっとこの先祖のものなんや。日本人の中には、ちゃんと血の記憶があるんやから」
そう言って源兵衛さんはにやりと笑った。奥座敷にさっと風が吹き渡る。君たちも立ち上がれ、とその眼は言っている。